子どもの言動をどこまで見守り、どこから手助けをするか。
なかなか悩みが尽きない、永遠のテーマですよね。
私自身、3歳と1歳の子どもと過ごしていて悩むことが多いです。
また、看護師として患者さん、利用者さん、ご家族の方と関わる際にも、同じようなことで悩みます。
子ども相手に限ったことではなく、教員と生徒、上司と部下、家族間、友人間などでも、このような悩みをお持ちの方がいらっしゃることと思います。
そこで今回は、精神科看護師が考える「子どもの自立心と安心感を育てる見守り方」を、老子の名言、ウィニコットが提唱した考え方と併せてお伝えします。
育児中の皆さまだけでなく、悩めるすべての方へ、何かしらのヒントをお伝えできれば幸いです。
老子の名言「授人以魚 不如授人以漁」
老子の名言「授人以魚 不如授人以漁」は、「魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えよ(=ある人に魚を与えたらその人は一日食べていけるが、魚の捕り方を教えたら一生食べていける)」ということを伝えています。
訪問看護師時代に上司から教わり、まさにその通りだなと痛感した言葉です。
前置きになりますが、以前私の勤めていた職場(精神科訪問看護ステーション)では、利用者の皆さまに「卒業」していただくことを目標としていました。
訪問看護ステーションごとに特色がありますが、利用者が支援を受け続けるのではなく、最終的に自身で生活を組み立てていけるようにする。
そのための支援をする。というスタンスを貫いていました。
漫然と支援を継続してお金をもらい続ければ、会社としては儲かるのです。
しかしそうではなく、「本当に、今、この方に、この支援が必要なのか」と熟考してケアを提供している点で、素敵な会社だなと誇りを持って働いていました。
もちろん、命の危機が迫っている方に「自分でやってください!」というわけではありません。
魚を与えるべきときには与え、捕り方を教えるべきときには教える。
子育てをする上でも、これを念頭に置きながら子どもと関わっています。という前置きでした。
完璧でなくほどよい母親(=good enough mother)であれ
わが家では現在、3歳娘と1歳息子と過ごしています。
娘の育休明けに復職しようかハゲそうなほど悩んだ末に、今しかないこの時期を堪能しようと、一旦退職することを決意しました。
そのほうが、丁寧な育児ができると考えたからです。
息子も生まれて2人の自宅保育をしながら副業をしていましたが、自分の休息時間を削りながらの活動に限界を感じ、保育園の力を借りることを決意しました。
自宅保育と保育園。子どもと過ごす時間の長さや諸々の優先順位は変わりましたが、どちらの時期も「子どもの行動をどこまで見守り、どこから手を貸すか」に頭を悩ませていました。
必要以上に手を貸してしまうと、相手が本来持つ力を奪ってしまうということは、看護学生時代から耳にタコができるほど聞いてきましたし、実際に現場でそう痛感する出来事も多々ありました。
学生時代の精神看護学の授業は興味深いものばかりでしたが、中でもウィニコット提唱の「ほどよい母親」の考え方がとても印象的でした。
乳幼児の心理に関するユニークな概念を数多く生み出したイギリスの精神分析家・小児科医のウィニコットの言葉に「ほど良い母親(Good enough mother)」というものがあります。これは、いわゆる普通の”ほどほどに良い”母親のことです。
ウィニコットは、完璧な母親による完璧な育児ではなく、この「ほど良い母親」によるほどほどの育児こそが乳児にとって大事だと考えました*1。「ほど良い母親」は、赤ちゃんの欲求に完璧に応えることは出来ません。時に見当違いのことをし、時に対応が遅くなり、時に応じられないこともあります。しかし、この不完全さこそ、赤ちゃんが自分の外側にある世界に気づいていくために必要なのです。
「この世界は必ずしも思い通りになるわけではない」と知ることが、この世界で生活をはじめるために必要なことなんですね。ほう。
そんなわけで、「安全な環境を整えてあげるから、大けがしない程度に、まずは自分で色々と試して冒険してみなさいな」というのが、私の育児モットーです
一人でできることはやらせてあげる、見守りや一部介助でできることは最低限手を貸す、全介助したほうがいいことは全介助する。
そこを見極めながら関わっています。
とはいえ、長女もまだ3歳ですから、普段は難なくできることでも「今日はやってもらいたいんだよバブぅ」という日もあります。
(どこまで自分でやってもらおうかなぁ、もう少し見守ろうかなぁ、そろそろ時間と私の心の余裕が限界だなぁ、いやでももう少し見守ろうかなぁ……)と迷った時にいつも思い出すのは、精神科の看護実習での出来事です。
自立とは?精神科看護実習で考えたこと
精神科実習の初日。受け持ちの患者さんから「病室の温度を下げてほしいって、看護師さんに伝えてください」と頼まれた。
その通りに伝えると、病棟看護師からは「あ〜!〇〇さんにうまいこと使われちゃったね」と。
はて、どういうことだろう。
決して嫌味なニュアンスではなく、言葉の本意としては
「精神科で治療をしている患者さんは、人との関わりでうまくいかないことが多いから、要求を自分で直接伝えるというのも治療の一つなんだよ」
「病室にこもりがちな患者さんだから、ナースステーションまで自分で歩いてくることも大事なんだよ」
ということでした。
なるほど。おもしろいじゃん、精神看護。
よし、患者さんの活動範囲を広げるためにも、低下してしまった機能を取り戻すためにも、できることはなるべくご自身でやっていただこうじゃありませんか。
それが看護というものだな。そういや座学でも散々「自力の活用が大事です」と言われてきたな。
そう思い、大学の指導教員にその日の学びを伝えたところ、「必ずしもそうとは限らないんじゃないかな。ほら、私たちだって人に甘えたい時はあるじゃん?普段は自分でやってるけど、今日は疲れたからやってもらいたいな〜って」と。
ほう、今度はそうきましたか。
実習あるあるの、病棟看護師と大学の指導教員との間で意見が割れるやつですね。
特に精神科での治療は、医療者自身の価値観が大きく反映されるので、いろんなアプローチがあって面白い。おもしろむずかしい。
当時の私は病棟看護師の考えに近かったのですが、大学教員の言葉がじわじわと沁みてきたのは、数年後に看護師になってから。
自立を促すのは関係性を築いてから
夜勤明けに、疲労困憊でマッサージ店に駆け込んだときのこと。
施術後にセラピストさんが「ご自宅でもこんなふうにマッサージしてみてください。ここの筋肉が…」とご丁寧に伝えてくれた。
きっと、マッサージに通わずにセルフケアで賄えるのがお客さんにとって幸せなことだろう、セルフケア能力を高めることが大事だろう、という想いからでしょう。
わかってる。セラピストさんが優しさゆえに掛けてくださった言葉なのはわかってるんだ。
それでも「んなこたぁわかってるよ、今の時代、調べりゃいくらでも出てくるよ。そういうことじゃないんだ、今はただひたすらに身を委ねたいんだ」と、少しいらだってしまった自分がいた。
今思い返してみれば、あなたはセルフケア能力が低い人だ、知識がない人だと言われているような気がして、恥の感情が生じていたのかもしれない。
もしくは、他人に癒されたいと思って駆け込んだのに、セルフケアの重要性を伝えられて、なおさら疲労感が強まってしまったのかもしれない。
しかも、初対面。
どんな背景があって来店したのか、普段の自宅での過ごし方はどんな様子なのか、初対面であってもそんな会話を挟んでからだとスッと受けとれたのかもしれない。
そこでようやく、前述した大学教員の言葉を思い出す。
「必ずしもそうとは限らないんじゃないかな。ほら、私たちだって人に甘えたい時はあるじゃん?
普段は自分でやってるけど、今日は疲れたからやってもらいたいな〜って」
あああああ…
ただひたすらに甘えたいときもあるよねぇ。
そうだよねぇ。それが人間ってもんだよねぇ。
そんな経験から、大人相手に安心感を与えつつ自立を促すサポートをするには、
- 相手と関係性を築けているか
- 相手がどのくらいその行動・状況に慣れているか
- 相手が普段と変わった様子はないか
- 相手の自立心に配慮した声掛けになっているか
- そもそも、その自立を促す必要が本当にあるのか
これを念頭に置く必要があると感じました。
精神科実習の出来事の答え合わせになりますが、今振り返ってみると「患者さんの要望を代弁する」で正解だったと思います。
出会って初日、まだ関係性を築けていないタイミングでしたからね。
自立を促すケアは、すでに関係性を築けている病棟看護師だからこそできるケアだったと思います。
その患者さんがいつもそうなのか、そのとき特別そうだったのか、どんな想いだったのか、私はそのとき背景をまったく知りませんでした。
そこで「ご自身でやっていただいたほうが、回復にもつながり云々~…」とお伝えしていたら、どうなっていたことでしょうか。ああ、恐ろしい。
子どもに安心感を与えつつ自立心を育むには
大人相手の事例を前述しましたが、子どもに安心感を与えつつ自立心を育てるという点でも、似たようなことが言えるでしょう。
- 「どんな状況でも自分でやらせようとしてくる親」ではなく、「本当に手助けが必要なときにはそうしてくれる親」であるか
- 子どもが初めてやることか、まだ経験が浅いことか、何度もやって慣れていることか
- 普段と変わった様子はないか、今の体調はどうか
- 子どもの言動の背景にある想いは
こんなことを意識してみるとよさそうですね。
具体的には
これ自分でやってみたい?それとも、今はまだお手伝いしたほうがいいかな?
もし難しかったら手伝ってあげるから、できるところまで自分でもやってみる?
自分でやりたいと思ったときがあったら、いつでも教えてね
元気がないときは全部やってあげるから、いつでも教えてね
いつもは自分でやってるけど、今日はどうしてやってもらいたいと思ったの?
いつもはやってもらいたがるのに、今日はどうして自分でやりたくなったの?
もしかしたら知ってるかもしれないけど、これはこんな風にやるといいみたいだよ
などと声を掛けて、子どもの逃げ道を作ってあげたり、背景を汲みとりながら関ってみるのはいかがでしょうか。
親が疲れているとき、時間の余裕がないときは?
ここまで読んで、「そんなことはわかってるよ!」「何回も試してるってば!」「そんなんで上手くいくならもうできとるわ!」と思った方。
そのお気持ち、ごもっともです。
そういうときは、もう親がやりやすい方法でやってしまいましょう。いいんです、いいんです。
この記事をご覧になっている方は、きっと普段からいろんな工夫をしながらお子さんと関わっていて、そのことはきっとお子さんにも伝わっています。
色々試した上で親の余裕がなくなりそうなときには、
ごめんね、本当はできるまでゆっくり見守ってあげたいんだけど、今は時間がないからやらせてもらうね
今日は疲れちゃったから、こっちでパパっとやらせてもらうね
などと伝えてもいいと思います。
誰かを見守るには忍耐力が必要ですが、自分の忍耐力が培われるまで待つことも、これもまた忍耐力がいることです。
あ~~~、くやしいけど今の自分の限界はここまでか~!それでもよくやった~
と自分を褒めながら、パパっと親がやってしまいましょう。それでいいんです。いつも本当にお疲れさまです。
今回の記事では、このことを一番にお伝えしたいと思っておりました。
おわりに
育児や精神医療や知識が増えるたびに、「理論上はそうだけどさ!そうなんだけど、人間そう簡単にはできてないよねぇ」と痛感することが山ほどあります。
打ちひしがれもしますし、そういう人間の不完全さに、面白みを感じることもあります。
育児の醍醐味でもありますし、私が精神科の看護師を続けている理由のひとつでもあります。
誰かの成長を見守るには
「相手が余裕があるときには魚の捕り方を教え、余裕がないときにはただ魚を分け与える。
ただし自分の魚を与えすぎない範囲で」
自分の心身を守るためには
「余裕があるときには魚の捕り方を覚え、余裕がないときにはただ誰かに魚を分け与えてもらう。
ただし相手の魚を奪いすぎない範囲で」
子ども相手にも大人相手にも、このことを忘れずに過ごしたいものです。
※こちらの記事は、2024年6月11日のnote投稿をリライトしたものです。

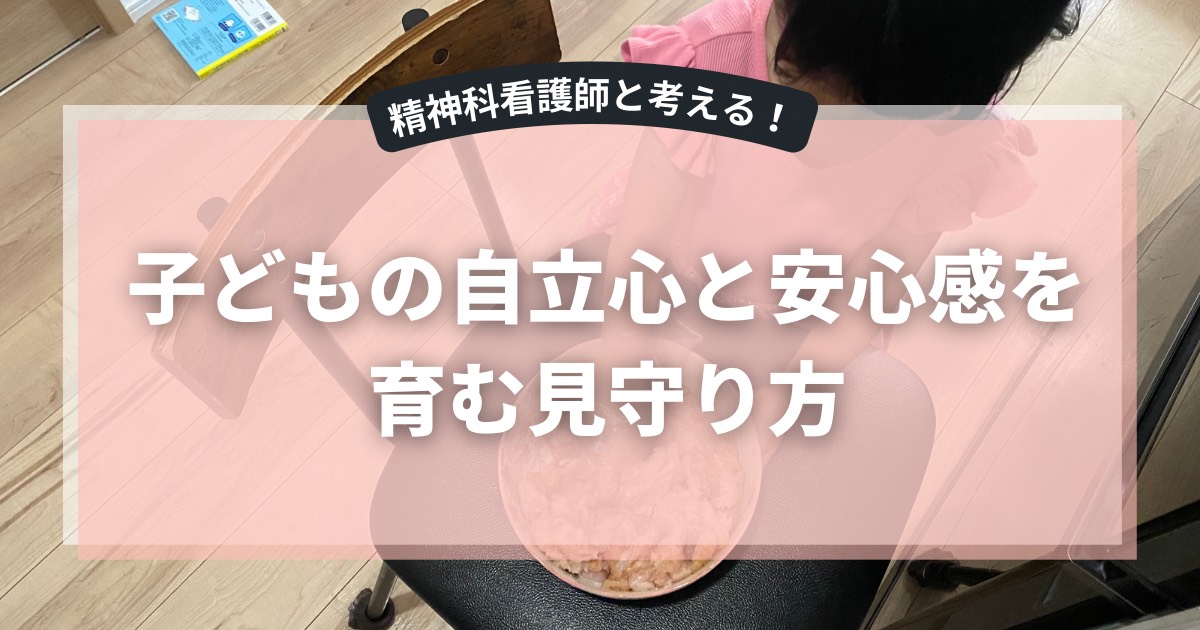
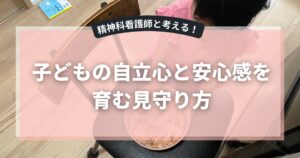
コメント