みなさん、今日も本当にお疲れさまです。
どんな一日になりましたか。
私はこれといった収穫がないまま夕方になってしまい、慌ててこの記事を書いています。
さて、早速お尋ねしたいのですが、みなさんは自分が何かしらの「依存症」だと感じたことはありますか。
ハマってるものはあるけど、依存症とまでいかない気が…
結構なお金と時間を費やしてるけど、これは依存症なのかどうか…
など、もしかしたら少なからず心当たりがあるかもしれません。
ちなみに筆者は、これ以上ハマりすぎないように気を付けないとな…と思いながら、競馬を楽しんでいます。
熱中しやすい性格なので、スマホゲームもやりすぎないように、なんとか自制心を保とうとしています。
「Life is a gamble.」 「人生はギャンブルだ」
という言葉がすきな筆者が、果たしてこの仕事をしていていいものなのか。
こちらの記事では、依存症治療に携わる精神科看護師が、依存症についてお伝えします。
- 依存症に興味がある
- 自分や周囲の人が依存症かもしれない
- やめたくてもやめられないことがある
- 大事になる前に早めに対策したい
こんな方は、ぜひお目通しください。
まずは大まかに「依存症とは」という内容をお伝えし、今後の記事では依存症の種類ごとに詳しく解説していきます。
この記事を書こうと思った理由
 ざらめくん
ざらめくん一人でも多くの方に依存症を正しく知っていただき、
誰かが治療を受けやすい社会に、
誰かが治療を受けることを見守る社会になってほしい。
叶うことなら、早い段階で依存症であることに気付き、苦しむ人を減らしたい。
この想いに尽きます。
- 一人で抱え込んでいるケース
- 周囲に迷惑が及んでいるケース
- 犯罪に至ってしまったケース
など依存症治療の背景はさまざまですが、誰かにとっての一助になりますようにと、願ってやみません。
そもそも「依存」「依存症」って?



「依存」「依存症」をそれぞれ広辞苑で調べてみると、
い-そん【依存】
(イゾンとも)他のものをたよりとして存在すること。
いそん-しょう【依存症】
ある物に頼ることをやめられない状態。
と書かれています。
まさにその通りで、
日常生活に何かしらの支障をきたしているにも関わらず、自分の力だけではやめられない状態のことを「依存症」といいます。
誰でも依存症になる可能性があります。
そして、誰でも治る可能性があります。
2024年に開催された「わたしたちの未来をひらく依存症啓発キャンペーン」では、従来の「ダメ。ゼッタイ。」に代わるキャッチコピーとして、西川佳乃さんの「誰でも、なる。誰でも、なおる。」という作品が大賞に選ばれています。
その時代を反映するかのように依存症の種類も増え、筆者が働いている職場でも新規患者数が徐々に増えつづけています。
適度に楽しむ範囲を超えて、やめたくても自分の力でやめられなくなっていることや物があったら、依存症のサインかもしれません。
依存症にはどんな種類があるの?
挙げればキリがない「○○依存症」
余談にはなりますが、精神科医が診断をする際には、DSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)という、アメリカの精神医学会が作成している診断基準を用いることが多いです。
※必要に応じて他の検査なども行いますので、これだけで診断がつくとは限りません。
1952年から何度か改定を重ねて、新たな疾患が加わったり疾患の定義が変更され、日本語版では2023年発行のDSM-5-TRというバージョンが最新のものになっています。


あっ、この名前を覚える必要はありませんよ。
ふーん、と軽く流していただいて構いません。
何が言いたいかと申しますと、このような本に正式に載っている依存症もあれば、例えばコロナ禍によく耳にした「マスク依存症」のような、医学的には認められていない「〇〇依存症」という通称もたくさんあります。
・DSM-5-TRに載っている正式名称ではないものもある
・医学的には認められていない通称のものもある
と前置きをした上で、わかりやすい名称でいくつか種類を挙げみますと
アルコール依存症、ギャンブル依存症、薬物依存症、カフェイン依存症、買い物依存症、クレプトマニア(窃盗癖)、性依存症、ストーカー、DV、ネット依存症、ゲーム依存症、ホスト依存症、マスク依存症、整形依存症…etc
など、挙げようと思えばいくつでも挙げられてしまいます。
本当に、時代が反映されていますよね。
平安時代には、蹴鞠(けまり)依存症とか、貝合わせ依存症とかあったのかな…(ボソッ)
依存症は大きく3つに分類される
依存症を大まかに分類すると、以下の3つに分けられます。
❶物質依存
→アルコール、薬物、たばこなど。特定の物質を摂取したときの刺激に依存する。
❷プロセス依存
→ギャンブル、ネット、買い物など。行動の過程で得られる刺激に依存する。
❸関係依存
→ストーカー、DV、親子や夫婦の関係など。特定の人間関係に依存する。
依存症の治療をされている方は、2つ以上の依存を合併する「クロスアディクション」という状態になっている場合もあります。






よく、依存対象が次々と移り変わる…っていう話も聞くよね。
依存するメカニズムは?
行動の強化と引き金
依存行動に限ったことではありませんが、そもそも人間には
「よい結果をもたらした行動をくり返すようになる」
という仕組みが備わっています。
先ほど挙げたお酒やギャンブルなどもそうで、
- お酒を飲んでいる間は、嫌なことを考えずに済んだ
- 誘われてギャンブルをやったら、たまたま大当たりした
など、よい結果につながった行動はくり返すようになり、次第に習慣になります。
決して悪いことではなく、よりよく生きていくために、とても健全なことですよね。
それが心身の支えになり、うまく生活が回っているようであれば(ここが重要)、健康的な依存だと言えるのではないでしょうか。



しかし、次第にコントロールが効かなくなってくると、依存対象が目の前にない状態でも、それに関連する引き金(きっかけ)があると、脳と身体が反応して欲求が生まれるようになります。
例えばお酒でいうと、
- よくお酒を買っているお店の前を通り、飲みたくなった(→場所の引き金)
- よく一緒に飲んでいる人から連絡があり、飲みたくなった(→人の引き金)
- よくお酒を飲むときに聴いている音楽が耳に入ってきて、飲みたくなった(→物の引き金)
- 土日に飲むことが多く、今週もまた土日になったため、飲みたくなった(→時間の引き金)
などです。
この引き金(きっかけ)は無数に増える可能性があり、依存行動につながらないようにするためには
❶自分にとって何が引き金になっているのか知ること
❷その引き金を可能な限り避けること
が大切になります。
「パブロフの犬」の実験
そもそも人間にはこういう仕組みが…とお伝えしましたが、人間に限ったことではありません。
「パブロフの犬」の実験
犬に餌を与えるときに同時にベルを鳴らすことを続けていたら、そのうち犬がベルの音を聞いただけでも(=引き金)、餌があるかのように唾液を分泌するようになった。
このように、本来は無関係なもの(ベルの音と唾液の分泌)が、学習によって結びつくことを「条件反射」と言います。
このことから、依存行動をやめられないのは意思の弱さではなく、もう脳がそういう仕組みになってしまっていることがわかりますね。



依存症はどうやって治療するの?
どんなアプローチがあるの?



ものすごく大まかに言えば、この2点です。
❶自分や依存症についてよく知る
・依存症のメカニズムを知る
・依存行動につながった背景を知る(家族の影響、友人からの誘い、仕事のストレス、など)
・依存行動の引き金を知る(行動に移すときの感情、場所、時間、状況、など)
❷環境を整える
・極力引き金を避ける環境をつくる
・自分の状況を伝えて、周囲の人に協力してもらう
・支え合いながら治療できる仲間を見つける
●医療・心理学的なアプローチ
・入院病棟での急性期治療
・デイケアや外来での治療プログラム参加
・精神科訪問看護の利用
・オンラインカウンセリングの利用
・薬物療法
・認知行動療法
など
●社会的・環境的なアプローチ
・自助グループの参加
・グループホームでの共同生活
・就労支援施設の利用
など
●その他自分でできること
・暇な時間を埋めるようなスケジュール管理
・日記やアプリを使った行動記録
・自己理解につながる認知行動療法アプリの利用
など
パッと思い浮かんだのはこのあたりでしょうか。
羅列するだけじゃ全然イメージできないよ
と思われた方もいらっしゃると思いますが、本当にその通りだと思います。
今回の記事は概論ということでざっくりと挙げ、今後の記事で各論としてひとつずつ丁寧にお伝えします。
筆者はどんな治療に携わっているの?
筆者は依存症治療を行っている施設のデイケアに配属されており、週6ペースで通っている方や、月1回ペースで通っている方など、さまざまな方と関わらせていただいております。
年齢は主に20~80代、対象疾患はアルコール、ギャンブル、薬物、性、買い物、ネット、ゲーム、クレプトマニア(窃盗癖)、ホスト…などの依存症を中心に、依存症以外のどの精神疾患の治療も行っています。
【業務の一例】
・デイケア内で与薬し、内服継続をサポート
・症状緩和のために向精神薬の筋肉注射
・治療プログラムに参加し、感情表出や自己理解をサポート
・生活が困窮しないように金銭管理をサポート
・他部署の就労支援につなげる
・ご家族や役所や他院との情報共有
など
今まで病棟や訪問看護の現場でも働いてきましたが、医療機関によっても治療方法が変わってくるので、そこの違いをまたゆっくりとお伝えさせてください。
さいごに
ここまでお目通しいただき、ありがとうございました。
なんとな~く、ぼんやりとでも、依存症というものが見えてきましたか。
簡単にまとめますと
●依存症は誰でもなり得る
●日常生活に何かしらの支障をきたしているにも関わらず、自分の力だけではやめられない状態のことを「依存症」という
●依存症になるのは意志の弱さではなく、そういう脳の仕組みになってしまうから
●依存症に至った背景や、依存行動につながる引き金(きっかけ)を知り、環境を整えることが大切
●自分自身をよく知るためには、治療プログラムや自助グループなどに参加し、自分のことを言語化したり、他の人の話を聞いて気付きを得ることが大切
こんなところでしょうか。
今後の記事では、疾患ごと、治療プログラムごと、医療機関ごと…など、様々な形で依存症治療についてお伝えしていきます。
感想コメントやSNSでのシェアも大歓迎です。
必要な方に情報が届きますように…!
くり返しにはなりますが、みなさん、今日も本当にお疲れさまです。

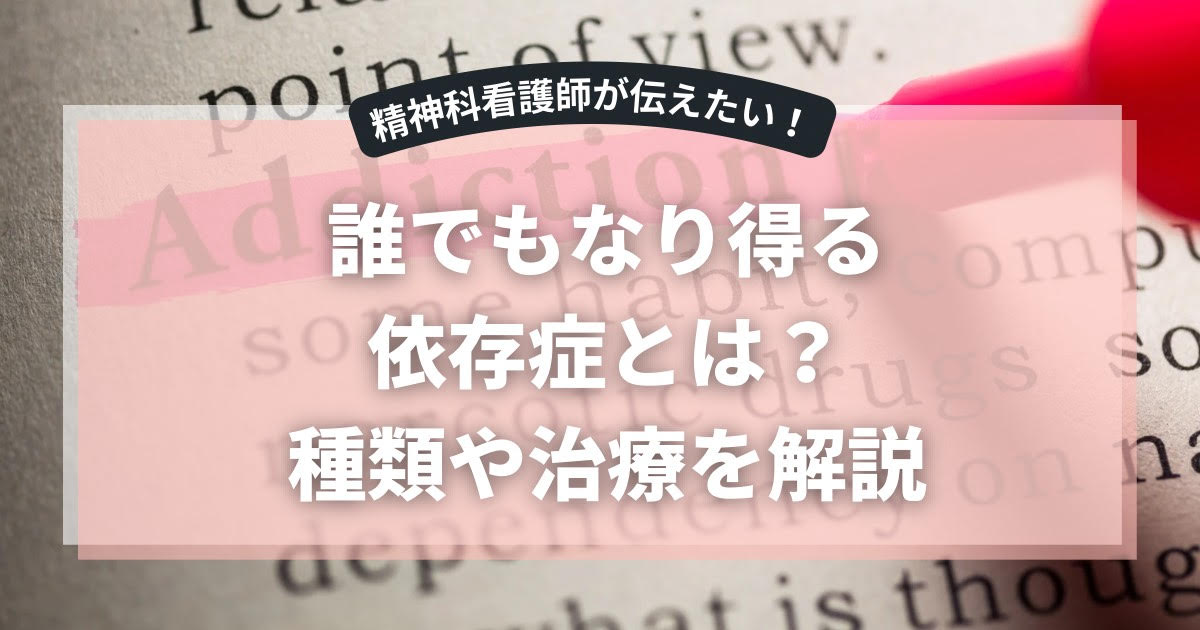
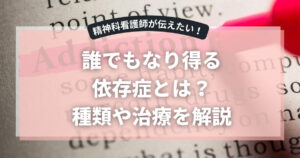
コメント