みなさん、今日も本当にお疲れさまです。
どんな一日になりましたか。
最近はあまりお酒を飲まなくなってきた筆者です。
・みんなでわいわい飲むことも、自宅でしっぽり飲むこともすき
・きらいなお酒はなく、何でも試してみたい性分
・ほろよい(商品名)でガチ酔いする体質
・飲むと真っ赤になり、耳が遠くなり、すぐに眠くなる
飲まなきゃやってらんねぇぜ!胃をアルコール消毒だっ
という時期もありましたが、最近は子どもを寝かしつけた後にやりたいことが多く(この記事執筆も然り)
お酒を飲むとポンコツになるから、飲まずに集中して取り組むぞ!
という生活が続いています。
ああ、たまには明日のことを考えずに、しこたま飲んで酔いつぶれたい…
酔っぱらいながら料理をして、「料理酒、料理酒~!」とフライパンにストロング缶(グレープ味)を注いでいた独身時代がなつかしい。
過去の自分聞いてるか、グレープ味はやめなさい。
そんなお酒との付き合い方をしている筆者ですが、精神科看護師として(とりわけ今は依存症治療がメインの現場で)、アルコール依存症の治療に携わっております。
前置きが長くなりましたが、今回は
- お酒をやめたくてもやめられないご本人様
- そのご家族、知人、支援者の皆さま
- 上記には当てはまらないが興味がある
という方に向けて、アルコール依存症の治療の一つである「抗酒剤」「断酒補助剤」と呼ばれるお薬についてお伝えします。
 琥珀くん
琥珀くん- アルコール依存症の治療とは?
- 抗酒剤、断酒補助剤とは?
- 効果、副作用、服用上の注意点は?
それでは、はじまりはじまり。
今回の記事を書こうと思った理由



筆者は精神科救急病棟(入院)→精神科訪問看護→依存症治療施設(外来やデイケア)といった現場で働いてきましたが、正直なところ、アルコール依存症について深く学びはじめたのは訪問看護の仕事に転職してからです。
入院病棟時代は「アルコールの離脱症状で入院されてきた方の急性期治療」がメインでした。
具体的には、さまざまな離脱症状を軽くするために、
・水分やビタミンを補う点滴をする
・肝臓の内服薬を与薬する
・動けない方の身の回りのお世話をする
といった、まずは最低限の身の安全を守るための補助をしておりました。
急性期を脱するとすぐに転院・退院されること多く、私自身院内の回復プログラムに関わる機会がなく、ゆっくりとお話させていただくことが難しいような現場でした。
訪問看護に転職してからは、ご自宅で落ち着いて対話ができる体調の方が多く、抗酒剤や自助グループなどについても教えていただくようになりました。
ようやく「アルコール依存症の治療に携わりはじめた」と実感がわいたのを覚えています。
何をお伝えしたいかと申しますと、職場によっては抗酒剤について詳しくない専門職も多く、ましてやそうでなければご存じない方も多いと思いましたので、「こんなものがあるんだ!」と知っていただく機会になりましたら幸いです。
アルコール依存症の治療とは?



まず、依存症全般についてはこちらの記事をご参照いただけますと幸いです。
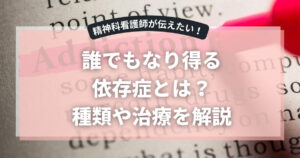
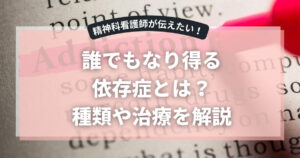
アルコール依存症の治療内容は、
・入院治療(離脱期の治療、回復プログラムの参加など)
・外来通院(診察、デイケア通所、回復プログラムの参加など)
・精神科訪問看護
・就労支援事業所や地域活動センターなどへの通所
・自助グループなどの当事者会、家族会の参加
・薬物療法(抗酒剤、断酒補助剤、飲酒量低減薬)
などが挙げられます。
- 生命が危険な状態における心身の治療
- 少し落ち着いてから、経緯、引き金、生活の工夫、今後の希望などを話し合う治療
- 就労やその他望む生活に向けての準備活動
といったところでしょうか。
今回の記事は、その一つである「薬物療法」にあたります。
抗酒剤や断酒補助剤とは?
抗酒剤とは
抗酒剤とは、「お酒を受けつけないような身体にする薬」のことを言います。
嫌酒薬と呼ばれることもあります。
抗酒剤を服用すると、ほんの少しお酒を飲んだだけでも吐き気や動悸がして気持ち悪くなるため、「お酒を飲みたくない」という状況を自分で作り出すことができます。
え、やだよ。お酒飲めなくなるじゃん
と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、本気で飲酒をやめたいと思う方にとって、心強い支えとなります。
近い例を挙げると、最近話題の「タイムロッキングコンテナ」でしょうか。


このケースにしまうことで一定時間スマホを使えなくなり、デジタルデトックスになるというスマホ我慢グッズです。
そう、それだ。
抗酒剤は「お酒我慢薬」といったらイメージしやすいかもしれません。
服用の注意点は後ほど詳しくお伝えしますが、抗酒剤を服用したあとに大量に飲酒すると、命に関わる危険性があるため、ご本人様がきちんと理解した上で服用する必要があります。
抗酒剤に限ったお話ではありませんが、「ご家族の方や支援者の方が、ご本人様が気付かないようにこっそりと飲ませる」…なんてことがないようにしてください。
(もちろん、筆舌に尽くせないご事情があることは、重々承知しております…)
断酒補助剤とは
断酒補助剤とは、「お酒を飲みたいという欲求を抑える薬」のことを言います。
前述した抗酒剤は「お酒を受けつけないような身体にする薬」でしたが、断酒補助剤は飲みたい気持ち自体を抑える薬であり、服用後にお酒を飲んでも気持ち悪くなることはありません。
・抗酒剤と断酒補助剤は併用することができる
・すぐに「飲みたい」と感じるような、アルコール依存特有の神経活動を抑える
・服用後に飲酒しても、抗酒剤とは違って気持ち悪くならない
・抗酒剤よりも肝臓や心臓にかかる負担が少ないため、持病がある方やご高齢の方でも服用しやすい
といった特徴があります。
抗酒剤や断酒補助剤の効果とは?



❶お酒を我慢しやすくなる
・「自分はお酒をやめたいんだ」と改めて認識することにつながる
・そもそも飲酒の欲求がわきづらくなる(断酒補助剤)
・お酒の誘惑が舞い込んできた際に(知人からの誘い、コンビニやスーパーでお酒を見かける、飲食店の前を通る等)、服用していることがストッパーとなる
❷家族や知人や職場の人など、周囲の人の安心にもつながる
・内服している姿を見せたり、内服していることを伝えることで、「外出して飲酒するのではないか」「飲酒した状態で出勤しているのではないか」などといった周囲の方の不安を軽減することにもつながります。
ご本人様にメリットがあるのはもちろんのこと、周りの人の安心にもつながる御守りとなります。
抗酒剤の種類や副作用



シアナマイド
・無色透明、無味、無臭の液体薬(冷所保存)
・服用後すぐに効果があらわれ、約24時間持続する
→「今日だけお酒を我慢しよう」という日にも最適
・副作用として、主に湿疹があらわれることがある
ノックビン
・白色の粉薬(室温で保存)
・服用後1~2週間後に効果があらわれる
・服用をやめても、2~4週間ほどは効果が持続する
→シアナマイドだと飲み忘れてしまう方、シアナマイドで副作用が出た方が服用されることが多い
・副作用として、主に湿疹があらわれることがある
・長期間服用すると、稀に神経系などの副作用がみられることがある
断酒補助剤の種類
レグテクト
・白色の錠剤、通常は1日3回毎食後に服用
・副作用として、主に嘔気や下痢などの消化器症状があらわれることがある
・内服だけに頼らず他の治療と併用することが大切
・抗酒剤(シアナマイドやノックビン)との併用も可
抗酒剤の効果的な服用方法は?



「各々の主治医の指示通りに服用してください」という大前提がある上で、一般的に推奨されている服用方法や、筆者の職場で行われている方法をご紹介します。
●効果的な服用のタイミング
抗酒剤はどの時間帯に服用しても効果が得られますが、「朝」や「夕方」に服用される方が多い印象です。
朝→「よし今日もお酒を飲まない一日にするぞ」と、前向きに行動に移しやすい時間帯。
夕方→夕方から夜にかけて、飲食店がにぎわい始める、アルコールのCMが流れ始める、食事の誘いがある、退勤時間になるなど、一般的に飲酒したくなりやすい時間帯であるため、その前に服用しておくとよい。
一度飲酒欲求がわいてしまうと、そこから抗酒剤を飲むことはなかなか難しいため、予防的に朝一番に服用している方が多い印象です。
●服用方法や服用場所
筆者の職場で関わらせていただいている皆さまは、
・自宅で一人で服用する
・外出前に家族の前で服用する
・グループホーム(治療上の共同生活)で同居者と同じタイミングで服用する
・通院時(外来やデイケアなど)に職員の前で服用する
といった方法をとられている方が多くいらっしゃいます。
服用回数は、1日1回の方も、朝晩2回の方もいらっしゃいます。
シアナマイドのみ、ノックビンのみ、シアナマイド+ノックビン、そこに断酒補助剤のレグテクトが加わったり、レグテクトのみ服用…など、主治医と相談して各々に合った方法で服用されています。
抗酒剤の服用後に飲酒してしまったら?



元々の体質、飲酒量、薬への耐性にもよるため、一概にはお伝えできませんが、
・一口や数滴の飲酒でも身体に影響が出る可能性がある
・大量飲酒では命に関わる可能性がある
といった危険がございます。
服用後に飲酒をしてしまった際には、かかりつけの精神科や内科にその旨を伝えて、診察を受けてください。
必要に応じて、点滴治療などをすることもございます。
また、意図的な飲酒ではなくとも、「間違えてアルコール入りのお菓子を食べてしまった」「調味料の加熱が不十分であった」というケースもございますので、身の回りのアルコールには十分お気をつけください。



でもそれだけ、正しく服用したらお酒をやめる強い味方になるってことだね。
ちなみに、飲酒量低減薬とは?



ここまできて、またよくわからないのが出てきた…!
飲酒量低減薬とは、「節酒を目的とした薬」のことを言います。
前述した抗酒剤や断酒補助剤との違いは、ずばり「治療目的」です。
・抗酒剤→断酒(お酒を完全に断ち切る)が目的
・断酒補助剤→断酒(お酒を完全に断ち切る)が目的
・飲酒量低減薬→節酒(飲酒することを前提に、飲酒量を減らす)が目的
アルコール依存症の内服治療の歴史をたどると、長年抗酒剤(シアナマイドとノックビン)の2種類だけでしたが、2013年に断酒補助剤のレグテクトが日本で販売開始となり、2019年には飲酒量低減薬のセリンクロが販売開始となりました。
近年のアルコール依存症の治療では、断酒だけではなく「ハームリダクション(=飲酒による不利益を可能な限り軽減する)」という考え方が少しずつ定着しています。
従来は「断酒あるのみ!」という治療方法が主流でしたが、「節酒にして、健康被害が少しでも減ればいいじゃん」と考える専門家も増えてきました。
※断酒か節酒かというのは本当に奥深い話題で、例えば節酒にできるならもちろんそうするに越したことはないけど、「病院や施設などの集団治療の場で節酒の方がいらっしゃると、断酒治療をしている方に影響が出てしまう」「みんなで頑張って断酒しよう!という結束力があるからこそ、治療のモチベーションを維持できている方も多い」「そもそも節酒で抑えられるならはじめからそうしているだろうし、脳のメカニズムとしてそうはならなかったから、大量飲酒・連続飲酒のアルコール依存症という状態になってしまったわけで…」など、専門家の間でも意見が分かれているのが現状です。(オタク特有の早口)
さいごに
ふぅ。いかがでしたでしょうか。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
アルコール依存症の薬物療法といっても、いろんな方法や歴史があり奥深いですね。
誤解のないようにお伝えしたいのは、「アルコール依存症の治療をするなら、必ずこれらの薬を服用してください!」と押し売りをしたいわけではございません。いや、本当に。
こちらの記事では「へぇ、こんな方法もあるんだ」と、まずはアルコール依存症の薬物療法について情報共有できれば幸いです。
必要な方に情報が届きますように、SNSで記事のシェアをしていただけるだけでも大変励みになります。
みなさん、いつも本当にお疲れさまです。
きょうも生きててよかったです。

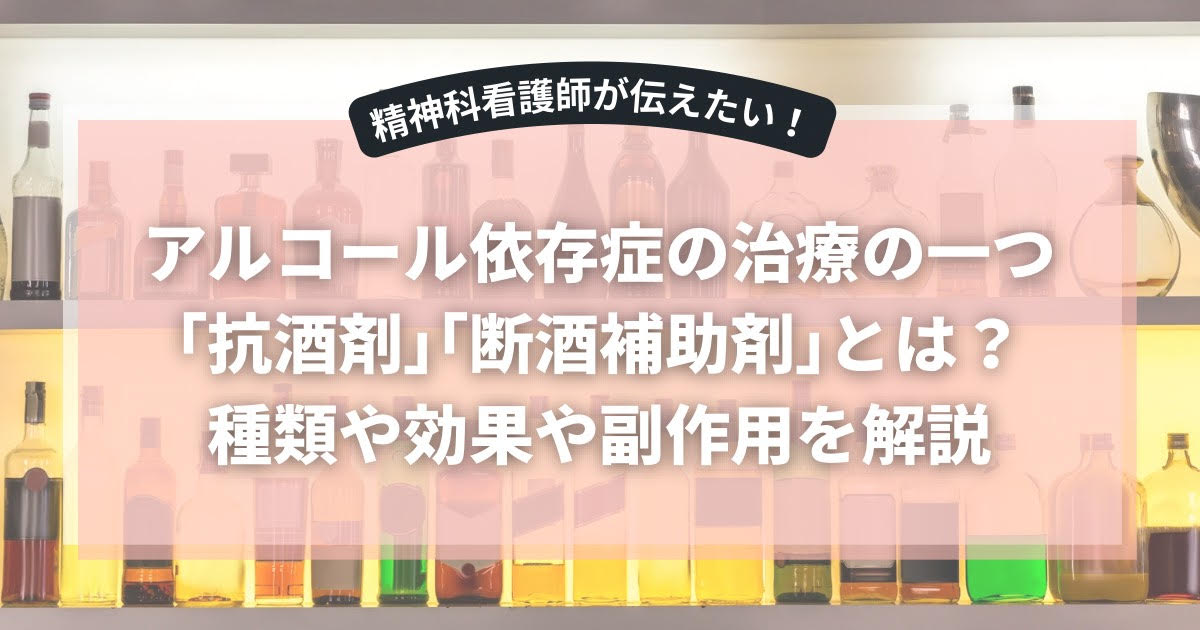
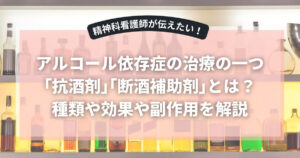
コメント